9月に読んだ本の中から、心に残った作品をジャンルを問わず厳選してご紹介します。日本の文化や歴史を再認識できる本や、若かりし日の勉強を思い起こす一冊など、日常生活で一息つきたいと選んだラインナップです。読書習慣を続けたい方や、次の一冊を探している方にとって、ヒントになれば幸いです。
田辺聖子の万葉散歩/田辺聖子
田辺聖子さんが『万葉集』の魅力をわかりやすく解説してくれた一冊です。前半は、昭和初期に主婦の友社で作られた「万葉百首繪かるた」から珠玉の歌が紹介されています。「万葉百首繪かるた」には、当時の読者投票で選ばれた歌が使われていて、千年前から、昭和時代、現代まで続く、日本人が愛してやまない美しさが凝縮されています。
さて、後半は、田辺聖子さんが好きな歌を集めています。田辺聖子さんの古典案内や小説が好きな読者には、やっぱりこういう歌が好きなんだーと、納得しきりの内容でした。

この美しい万葉の世界観を理解できるなんて、『日本人でよかった!』と思える一冊でした。冒頭から、志貴皇子(しきのみこ)、額田王(ぬかたのおおきみ)の歌で始まり、万葉の世界に引き込まれます。
あの歌もこの歌も、お気に入りとして記憶したくなります。ああ、自分の記憶力のなさが悲しい・・・。こんな歌を諳んじることができたら、素敵に年を重ねているといえそうです。
冒頭で心をつかまれた志貴皇子の歌。志貴皇子は天智天皇の第七皇子。天武朝を生きた彼が、春の訪れを歓んだ歌。
石走る垂水の上のさわらびの萌え出づる春になりにけるかも
みんな大好き額田王の歌。元カレの天武天皇(大海人皇子)との応酬も美しい一首。
あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る
天智天皇による豪壮雄大な歌。万葉の王者の風格が現れていまます。
わたつみの豊旗雲に入日さし今夜の月夜あきらけくこそ

後半は田辺聖子さんの好きな歌ということで、「詠み人知らず」の歌や、「東歌」、「防人の歌」が多く紹介されています。田辺さんの小説を読んだことのある方なら、なるほどと思うはず!
前半の勇壮明媚な歌も好きですが、万葉の人々の素朴で飾らない歌だからこそ、千年以上もこの国で愛されているのだとつくづく思いました。ここにあげきれませんが、どれもこれも覚えておきたい歌ばかりでした。
中学生の頃に習った「防人の歌」。あの頃よりも、今のほうがしみじみと真情が伝わってきます。
父母が頭掻き撫で幸くあれて言ひし言葉ぜ忘れかねつる
こちらも「防人の歌」です。
韓衣裾に取り付き泣く子らを置きてぞ来のや母なしにして
見るだけでわかる微分・積分/冨島佑允
高校以来の微分・積分に、本当に見るだけか~、数式は要らないのか~、と恐る恐る手に取った一冊。看板に偽りなく、難しい計算をしなくっても、40代のおばちゃんでも、微分・積分って何のためにやっていたのか。何に役立っているのか理解できました。
①微分で事象の小さな変化を計算する
②積分で、小さな変化を積み上げる
③現在に、変化の積み上げを足し合わせて、未来を予測する

数学が苦手でも読めますが、高校数学をぼんやりとでも記憶していれば、あの記号にはあんな意味があったのか!あの頃知りたかった!と思うははず。(私も悔しかった)大人の頭の体操にうってつけの一冊でした。
現在でも役立っている微分・積分の事例を解説されていますが、私は「飛行機の揚力」と「都市計画」で目から鱗が落ちました。
ビジネスで未来を予測するにも役立つのでは!と勝手に妄想が膨らみます。
水滸伝 一曙光の章/北方謙三
十二世紀の中国、北宋末期。腐敗した政府を倒そうと立ち上がった漢たちの物語。あまりにも有名な物語、有名な著者ですが、実は読んだことがありませんでした。予備知識ゼロで読み始めましたが、まだまだ序盤も序盤なのに、次から次へと個性的なキャラクターが登場します。
- 王進・・・禁軍武術師範
- 林冲(豹子頭)・・・禁軍武術師範代
- 魯智深(花和尚)・・・放浪の僧
- 史進(九紋竜)・・・華州史家村の保正の息子
- 宋江・・・鄆城県の役人

全十九巻。ずっと気になっていて、ついに一巻に手を出してしまいました。果たしてこれからどう展開するのか。一巻では、心の中で『林冲ーーーーー!!!』と叫びながら読みました。とにかく林冲の先行きが気になって仕方がありません。一巻の推しは林冲でした。
江戸の組織人/山本博文
現代よりも格段に身分序列のあった江戸時代。幕府の組織を中心として、江戸時代の組織の在り方と、組織に生きた武士たちの実像を解説してくれます。町奉行、勘定奉行、同心、与力、老中、若年寄、目付、目明し、甲府勤番などなど、時代劇では聞いたことのある役職ですが、実際の仕事内容やどうやって出世していくのか、新しい知識が盛りだくさんの一冊でした。
町奉行は南北月番の交代制。ここまでは知っていましたが、南北それぞれ与力は二十五名、同心は百名。幕末で増員されるまでは、たった二百五十人ぽっちで江戸の町を守っていました。
しかも現代の警察だけでなく、奉行所は行政と司法まで担っていたのです。
そこで、同心たちは自分たちのポケットマネーで目明しを雇い捜査の手足としていました。時代劇で悪徳目明しが登場するのも納得の仕組みでした。

同心と目明しの関係もですが、江戸時代の武家組織では、往々にしてポケットマネーで仕事をすることが多かったようです。かの有名な長谷川平蔵も然り。雇用というよりも、奉公という意識だったのかもしれません。現代の日本社会でも見られる上司が”身銭を切る”という風習につながっているのかもと思いました。
現代と同じく江戸時代でも、藩政改革などにチャレンジするには、担当者から家老を経て、藩主まで承認を得てから断行されます。上手くいけば良いけれど、失敗すれば誰かが責任をとらなくてはいけません。責任の取り方は”切腹”です。そして、責任をとるのは、基本的には担当者。藩主を守るために、現場が犠牲になる。現代にも相通じるものを感じます。

職場でのいじめ、部下のやる気アップの方策、不良旗本のたまり場などなど、現代の日本組織に通じるものが多々ありました。良い悪いは別として、日本の民族的文化や組織風土が江戸時代にかなり出来上がっていたのだと納得しました。息苦しいところも多そうでしたが、目付がわざと咳ばらいをすることで己の存在を周囲に報せ、部下が処分されないように気配りしていたなど、日本人らしい細やかなエピソードはほっこりしました。
隼別王子の反乱/田辺聖子
ヤマトの大王の想われびと、女鳥姫と恋に落ちた隼別王子。大王の放った舎人らに、姫を奪われた隼別王子は、大王の宮殿を襲い、叛乱を起こしますが・・・。
古事記の中の濃密な物語が、田辺聖子さんの筆で美しくも凄絶に語られます。
- 隼別王子(はやぶさわけおうじ)・・・若く美しい皇子。ヤマトの大王の弟。大王の使者として訪れた湖の国で、女鳥と恋に落ちる。
- 女鳥姫(めどりひめ)・・・湖の国の姫君。隼別を愛する。
- 雄鹿(おじか)・・・舎人。隼別王子に仕える。
- 猪熊(ししくま)・・・隼別王子の従者。片目の大男。
- 大鷦鷯(おおさざき)・・・ヤマトの大王。若い娘を好む。
- 磐之媛(いわのひめ)・・・大鷦鷯の大后。大鷦鷯が若い后を迎えるのを妨害、追放、断罪、暗殺する。

若く美しい隼別と女鳥の恋。老いへの抗いゆえに、若さに嫉妬する大鷦鷯と磐之媛。五世紀の豊蘆原を舞台に、二組の男女の物語が、めくるめく展開されます。女鳥媛の領巾がひらひら舞う様や、隼別の黄金の甲冑姿、怪しげな太占などが、田辺聖子さんの紡ぐ美しい言葉で語られ、その世界観にすっかり魅了されてしまいました。王朝文学とは異なる、荒々しくも美しい物語。やっぱり田辺聖子さんの物語が大好きです!と叫びたくなる一冊。

大鷦鷯の大王は仁徳天皇なのでは。などと考えながら読むと、大王の他の逸話なども知りたくなり、古事記や古墳時代の沼に引き込まれていきます。
イクサガミ 人/今村翔吾
「イクサガミ」シリーズ第三巻。衝撃的な二巻のラストから引き続き、怒涛の展開。何を書いてもネタバレになるから書けないけれど、とにかく三巻を読んだら四巻へまっすぐGOするしかありませんでした。

登場人物の名前を書くだけでネタバレになってしまう。巻を重ねるごとに推しキャラが増えてゆく。なにこの本!!!恐ろしすぎる。
⇒「イクサガミ」シリーズや今村翔吾先生の作品に興味のある方はこちら
イクサガミ 神/今村翔吾
「イクサガミ」シリーズ最終巻。圧巻の最終巻。

幕末、明治ってとんでもない時代だったのだと圧倒されました。とにかく三巻を読んだら四巻に進まずにはいられません。三巻と合わせて四巻まで手元に置いておくことを強くおすすめします。完結記念に「木札」が当たるキャンペーンがありましたが、残念ながら当たりませんでした。「木札」欲しかったなあ・・・。
江戸「捕物帳」の世界/山本博文[監修]
江戸の警察組織(町奉行、与力、同心、岡っ引き、火付盗賊改方、関東取締出役など)や名裁判、刑罰などについてコンパクトに解説してくれでいます。

無性に時代劇が見たくなる一冊。でも最近は、「遠山の金さん」も「大岡越前」も「鬼平犯科帳」もない(涙)。
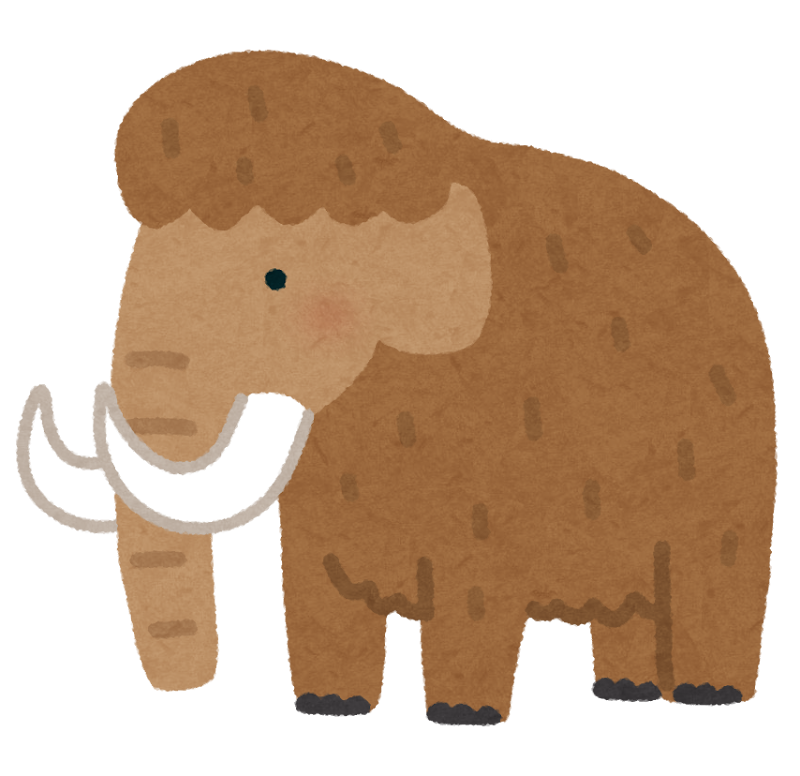



コメント