恋愛小説と平安小説の名手、田辺聖子さんによる浪漫あふれる小説やエッセイをご紹介します。中学や高校の古典では、田辺聖子さんの本に随分と助けられました。どの作品も、ページをめくるたびに雅な香りが漂ってきます。
王朝懶夢譚/平安女子の恋する和風ファンタジー
東宮へ入内する予定だった内大臣家の月冴姫ですが、宮の急死により3歳の新東宮が大人になるまでの10年もの間、花の盛りを無為に過ごすことを決められてしまいます。ある夜、運命を嘆く月冴のもとに、小天狗の外道丸が訪れます。意気投合した二人は、夜空を飛んで邪気のないイタズラを仕掛けます。イタズラの相手は、堅物で朴念仁の聖や、真面目な医師、東国から京へ上って来た武者などなど。月冴は果たして誰と結ばれるのか。王朝浪漫溢れる作品です。
- 月冴(つきさえ)・・・内大臣家の美しい姫君。花の盛りを無為に過ごす運命を嘆いている。
- 外道丸(げどうまる)・・・小天狗。「くちちちち」という笑い声が可愛い。
- 仁照(にんしょう)・・・堅物で朴念仁の聖。
- 麻刈(あさかり)・・・腕のいい医師。身分の上下なく病人を癒すことを志す。
- 晴季(はるとき)・・・東国の武者で田舎者。

「くちちちち」と笑う外道丸がとっても可愛く描写されています。小天狗の他にも、河童や化け狐など様々なあやかしが登場します。
本作は連作短編集となっています。一話ごとに相手が変わるのですが、月冴が最終的に誰と結ばれるのか目が離せません。
月冴と外道丸の会話中で、「レッスン」や「オムライス」といった現代語が飛び交います。田辺聖子さん視線の軽妙な語り口なのだと思いますが、そんな場面以外は、至って雅な王朝絵巻の世界がファンタジックに描かれています。
王朝懶夢譚のタイトルどおり、いくつになっても楽しめる浪漫溢れる小説です。若い頃よりも、40歳を超えて再々読のほうが楽しく読むことができました。
おちくぼ姫/田辺聖子流、王朝版シンデレラ
高貴な血を引く姫君なのに、意地悪な北の方(継母)にいじめられて、おちくぼんだ部屋で縫物ばかりさせられ、つけられた呼び名が「おちくぼ姫」。美しく優しい彼女を助けるのは、ネズミ、ではなくて、はしっこい乳姉妹の阿漕。ある日、都でも随一の評判の貴公子、右近の少将が姫君の噂を聞きつけて求婚します。次第に少将に心を開く姫君ですが、二人の前には恐ろしい北の方が立ちはだかります。はたして二人の恋の行方は・・・。
- 姫君・・・源中納言の娘で、皇族の血を引く美しい姫君。母親の死後、父親に引き取られるが、継母の北の方から床が落ち窪んだ部屋に押し込められ縫物ばかりさせられている。北の方から「おちくぼ」と呼ばれている。
- 右近の少将・・・都で評判の貴公子。最初は興味本位だったが、一目で姫君の美しさと優しさのとりこになる。
- 阿漕(あこぎ)・・・姫君の乳姉妹(乳母の娘)。美人ではしっこい性格。姫君の幸せな結婚のために奔走する。浮気せず姫君一人を幸せにしてくれる人でないと認めない忠義者。
- 帯刀(たちはき)・・・阿漕の夫で、右近の少将の乳兄弟。阿漕にぞっこんで頭が上がらないが、姫君を紹介しろとせっつく少将との間で板挟みになる。姫君と少将のために奔走する。
- 北の方・・・源中納言の正妻。四人の娘がいる。婿たちの繕い物を姫君に命じたり、持ち物を奪ったりと姫君に意地悪をする。未婚の四女、四の君にも三国一の婿を迎えたいと考えている。
本作は古典の「落窪物語」を題材に優しく書き下したものです。ですから、楽しく読みながら古典の知識までつけることができるという一石二鳥の作品となっています。しかも著者は以前にも「舞え舞え蝸牛」という作品で「落窪物語」を書かれていますが、今作ではさらに読みやすく優しい書きぶりとなっています。私は「舞え舞え蝸牛」も読みましたが、確かに数段やわらかい書きぶりとなっていました。

最初に読んだときは、シンデレラとの共通点の多さに、平安時代の作品なのにシンデレラをモデルにしたのではないかとびっくりしました。継子いじめの物語は古今東西、世界共通なのだと実感した次第です。そしてわかりやすく善玉と悪玉にわかれていて、姫君が幸せをつかむストーリーは何度読んでも最高の読後感です。
田辺聖子の古典まんだら(上)/上質な古典への誘い<神代~平安>
古典をこよなく愛する著者が、神代の時代の「古事記」から「万葉集」、「土佐日記」、「とりかへばや物語」などの平安時代までの愛すべき古典を解説してくれます。著者の他のエッセイに比べて、各古典作品や人物の解説が詳細にされていて、古典の入門書や歴史の勉強にももってこいの一冊です。収録されている古典作品は次のとおりです。
- 古事記
- 万葉集
- 土佐日記
- 王朝女流歌人
- 蜻蛉日記
- 落窪物語
- 枕草子
- 大鏡
- 堤中納言物語
- 今昔物語集
- とりかへばや物語
どこかで聞いたことはあるけれど、学校の古典や歴史では習わないスサノヲやヤマトタケルの物語や歌を知ることができます。私もどこかで聞きかじっていましたが、彼らの物語と歌を合わせて読むと格別です。
八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を
スサノヲが出雲に宮殿を造った際に、その地から雲が立ち昇ったので詠んだ歌です。
倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山隠れる 倭しうるはし
ヤマトタケルが最期に詠んだ歌。ミコトの魂は大きな白い鳥になって天に駆けていきます。
男女入れ替わりの物語です。権大納言には男女の子が生まれますが、活発な女の子は若君として育ち、大人しい男の子は姫君として育ちます。二人が評判の公達、深窓の姫君として出仕して騒動が巻き起こるというお話です。
現代ならよくある設定ですが、千年前の平安時代の古典文学での物語です。以前にも、別の著者による「とりかへばや物語」を読みましたが、一夫多妻という時代背景もあって、なかなかに読みづらい部分がありました。設定が抜群なだけに残念に思っていたのですが、こちらの解説では、田辺聖子さんがわかりやすく、かつ面白いエッセンスだけを抜き出してくれています。

つぶぞろいの名作古典が揃っています。田辺聖子さんの解説を読むと、それぞれの作品を読んでみたくなります。私は「古事記」と「堤中納言物語」「今昔物語集」を読みたくなりました。
田辺聖子の古典まんだら(下)/上質な古典への誘い<平安末期~江戸>
田辺聖子さんによる古典解説とエッセイ集。平安末期から江戸時代の次の作品や人物が対象です。
- 平家物語
- 方丈記
- 宇治拾遺物語
- 百人一首
- とはずがたり
- 徒然草
- 西鶴と近松
- 芭蕉・蕪村・一茶
- 古川柳
- 江戸の戯作と狂歌
高校古典でぶつ切りに習った物語の名場面がぎゅっと凝縮されています。若い頃にはわからなかった都落ちする人々の哀切が、年を重ねるとしっとりと伝わってきます。
- 密かに都に戻り、藤原俊成に勅撰集への和歌の掲載を願う平忠度。
- 「浪のしたにも都のさぶらふぞ」と幼い安徳天皇をなぐさめて、海へ入った二位の尼。
- 「見るべき程の事は見つ。いまは自害せん」と乳母子の伊賀家長と約束どおり一緒に海へ沈んだ平知盛。

平家物語には名場面が盛だくさんです。このエッセイ集は名場面の一部分だけが抜粋されているので、ぜひとも全編を通読したくなりました。
また、平家物語以外に「百人一首」の章で紹介されている和歌が、中高年の感慨をまさにそのとおりに詠ってくれていて、お気に入りの一首になりました。きっとお気に入りの物語や歌が見つかること請け合いの一冊です。
長らえばまたこの頃やしのばれむ憂しと見し世ぞ今は恋しき(藤原清輔)

あまりのイメージとのギャップに驚嘆したのは「とはずがたり」です。作品名だけは聞いたことがありましたが、やりたい放題の後深草院に衝撃を受ける作品です。昭和15年に国文学者に紹介されるまで知られていなかったというのですが、内容がショッキングすぎて門外不出になっていたのではないかという田辺聖子さんの説になるほどと思いました。
田辺聖子の万葉散歩/万葉集の魅力をぎゅっと凝縮
田辺聖子さんが『万葉集』の魅力をわかりやすく解説してくれた一冊です。前半は、昭和初期に主婦の友社で作られた「万葉百首繪かるた」から珠玉の歌が紹介されています。「万葉百首繪かるた」には、当時の読者投票で選ばれた歌が使われていて、千年前から、昭和、現代まで続く、日本人が愛してやまない美しさが凝縮されています。
さて、後半は、田辺聖子さんが好きな歌を集めています。田辺聖子さんの古典案内や小説が好きな読者には、やっぱりこういう歌が好きなんだーと、納得しきりの内容でした。

この美しい万葉の世界観を理解できるなんて、『日本人でよかった!』と思える一冊でした。冒頭から、志貴皇子(しきのみこ)、額田王(ぬかたのおおきみ)の歌で始まり、万葉の世界に引き込まれます。
あの歌もこの歌も、お気に入りとして記憶したくなります。ああ、自分の記憶力のなさが悲しい・・・。こんな歌を諳んじることができたら、素敵に年を重ねていると、胸を張って言えそうです。
冒頭で心をつかまれた志貴皇子の歌。志貴皇子は天智天皇の第七皇子。天武朝を生きた彼が、春の訪れを歓んだ歌。
石走る垂水の上のさわらびの萌え出づる春になりにけるかも
みんな大好き額田王の歌。元カレの天武天皇(大海人皇子)との応酬も美しい一首。
あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る
天智天皇による豪壮雄大な歌。万葉の王者の風格が現れていまます。
わたつみの豊旗雲に入日さし今夜の月夜あきらけくこそ

後半は田辺聖子さんの好きな歌ということで、「詠み人知らず」の歌や、「東歌」、「防人の歌」が多く紹介されています。田辺さんの小説を読んだことのある方なら、なるほどと思うはず!
前半の勇壮明媚な歌も好きですが、万葉の人々の素朴で飾らない歌だからこそ、千年以上もこの国で愛されているのだとつくづく実感。ここにあげきれませんが、どれもこれも覚えておきたい歌ばかりでした。
中学生の頃に習った「防人の歌」。あの頃よりも、今のほうがしみじみと真情が伝わってきます。
父母が頭掻き撫で幸くあれて言ひし言葉ぜ忘れかねつる
こちらも「防人の歌」です。
韓衣裾に取り付き泣く子らを置きてぞ来のや母なしにして
隼別王子の反乱/荒々しくも美しい古代の恋物語
ヤマトの大王の想われびと、女鳥姫と恋に落ちた隼別王子。大王の放った舎人らに、姫を奪われた隼別王子は、大王の宮殿を襲い、叛乱を起こしますが・・・。
古事記の中の濃密な物語が、田辺聖子さんの筆で美しくも凄絶に語られます。
- 隼別王子(はやぶさわけおうじ)・・・若く美しい皇子。ヤマトの大王の弟。大王の使者として訪れた湖の国で、女鳥と恋に落ちる。
- 女鳥姫(めどりひめ)・・・湖の国の姫君。隼別を愛する。
- 雄鹿(おじか)・・・舎人。隼別王子に仕える。
- 猪熊(ししくま)・・・隼別王子の従者。片目の大男。
- 大鷦鷯(おおさざき)・・・ヤマトの大王。若い娘を好む。
- 磐之媛(いわのひめ)・・・大鷦鷯の大后。大鷦鷯が若い后を迎えるのを妨害、追放、断罪、暗殺する。

若く美しい隼別と女鳥の恋。老いへの抗いゆえに、若さに嫉妬する大鷦鷯と磐之媛。五世紀の豊蘆原を舞台に、二組の男女の物語が、めくるめく展開されます。女鳥媛の領巾がひらひら舞う様や、隼別の黄金の甲冑姿、怪しげな太占などが、田辺聖子さんの紡ぐ美しい言葉で語られ、その世界観にすっかり魅了されてしまいました。王朝文学とは異なる、荒々しくも美しい物語。やっぱり田辺聖子さんの物語が大好きです!と叫びたくなる一冊。

大鷦鷯の大王は仁徳天皇なのでは。などと考えながら読むと、大王の他の逸話なども知りたくなり、古事記や古墳時代の沼に引き込まれていきます。
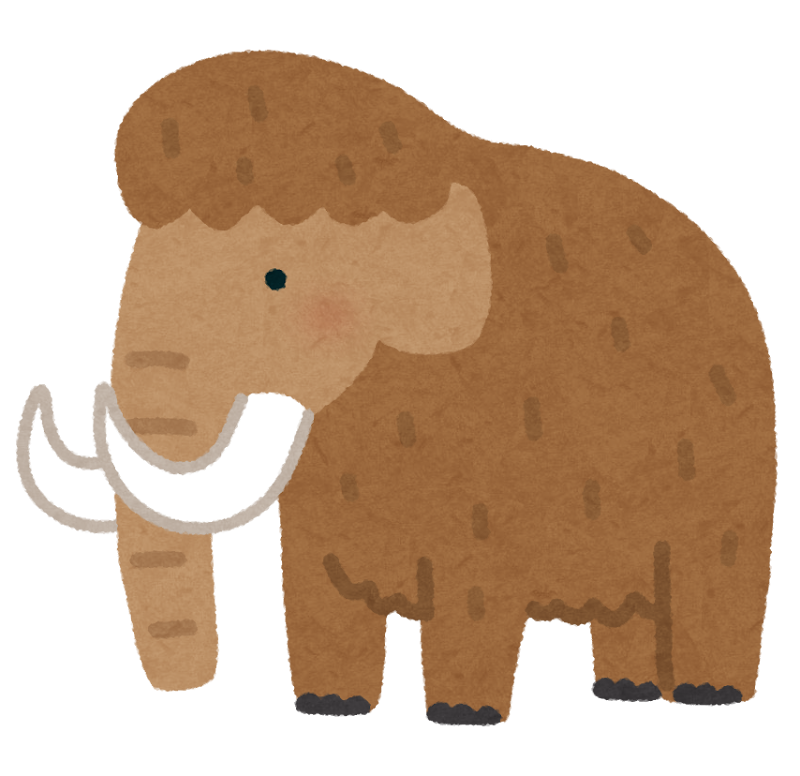



コメント