明治維新、文明開化、大正浪漫、こんなワードに魅力を感じる人におすすめのミステリを紹介します。
刀と傘/伊吹亜門
慶応三年、新政府と旧幕府の対立に揺れる幕末の京都で、若き尾張藩士・鹿野師光は一人の男と邂逅します。名は江藤新平。後に初代司法卿となり、近代日本の司法制度を築く人物です。二人の前には、時代の転換点ゆえに起きる事件が次々に待ち受けます。維新志士の怪死、密室状況で発見される刺殺体、処刑直前に毒殺された囚人。維新から明治の世へと移る動乱の時代を背景として、二人の名探偵が不可解な事件の謎を解き明かす連絡短編集です。
・鹿野師光(かのもろみつ)・・・若き尾張藩士。維新志士の怪死事件をきっかけに、江藤新平と縁を結ぶ。
・江藤新平(えとうしんぺい)・・・佐賀藩士。後に初代司法卿となり、近代日本の司法制度を築く。
本作は、5つの短編(「佐賀から来た男」・「弾正台切腹事件」・「監獄舎の殺人」・「桜」・「そして、佐賀の乱」)からなる連作短編集となっています。幕末明治の張りつめた空気感が伝わってきて、歴史小説としても読みごたえ十分ですが、個々の物語で発生する事件のロジックも秀逸で、ミステリ小説としても超本格です。

江藤新平は実在の人物です。私は歴史に疎くてその偉業を知りませんでした。本作がきっかけで江藤新平に興味を持ち、留守政府、明治六年政変などを知るきっかけになりました。物語の中でも、江藤新平はなんとも魅力的な人物に描かれています。
5つの短編それぞれに、誰が(フーダニット)、どうやって(ハウダニット)が緻密な論理の組み立ての上に成り立っています。それでも私はこの作品をホワイダニット(なぜ)の傑作だと思うのです。例えば、「監獄舎の殺人」では、死刑執行の当日に、獄舎に囚われた死刑囚が毒殺されます。もちろん誰がどうやって毒を盛ったのか、も気になる点ですが、やはり放っておいても今日死刑になる囚人を”なぜ”毒殺したのかが気になります。もちろん物語では、読者が納得できる理由が解き明かされるのです。

短編集では、通常、一番好きなのはこの物語というのがあります。しかし、本作はどの物語も魅力的すぎて選ぶことが難しいくらいの粒ぞろいです。脂汗をかいて選ぶのなら、「佐賀から来た男」「監獄舎の殺人」の二作が一等心に刺さりました。
開化鉄道探偵/山本巧次
明治12年。鉄道局技手見習の小野寺乙松は、局長・井上勝の命を受け、元八丁堀同心の草壁健吾を訪問します。建設中の鉄道工事現場で続発する、不審な事件の調査を依頼するためでした。新政府に協力する気のない草壁でしたが、日本の近代化のためには、鉄道による物流が不可欠だと訴える井上と小野寺の熱意にほだされます。ところが調査へ赴く小野寺と草壁のもとに、工事関係者の転落死の報が届けられるのです。
・小野寺乙松・・・工部省鉄道局の技手見習。生真面目な性格。
・草壁健吾・・・維新前は切れ者と評判だった、元八丁堀同心。
・井上勝・・・工部省鉄道局長。長州五傑の一人。
・国枝喜一郎・・・逢坂山トンネル工事の総監督。
・ウィリアム・カートライト・・・お雇い機関士。
事件の舞台は、京都・大津間の鉄道建設に際して、その区間に位置する逢坂山トンネルの工事現場です。当時の鉄道建設は、お雇い外国人に高額な報酬を払って行うことが当然でした。逢坂山トンネルは、ましてや日本初の山岳鉄道です。井上局長は、これを、日本人だけの技術で建設しようとしていたのです。ですが、急激な近代化には影も生まれます。作中でも、鉄道開設に伴い、仕事を失った船問屋や馬子が登場します。また、薩長の権力争いや、日本の鉄道敷設の利権を争う西欧列強の姿など、時代の光と影が描かれています。

日本初の日本人だけの手による鉄道建設。それをミステリの舞台にするなんて、さわりだけで面白そうだと手に取りました。しかも著者は、鉄道会社のサラリーマンとして三十年以上のご経歴があるとのこと。鉄道黎明期の様子が詳細に描かれ、ぐいぐいと引き込まれてしまいました。
物語の主役は、ホームズとワトソン役である、草壁健吾と小野寺乙松のコンビです。しかし、本作で私が最も魅力的に描かれていると感じたのは、井上勝鉄道局長でした。作中では、長州五傑の一人とされていますが、史実でも、幕末の動乱期に、苦心して渡英留学し、日本の近代化のために学んだ傑物です。作中では、鉄道局長にもかかわらず、筒袖に脚絆の工夫姿で鶴嘴(つるはし)をかついで現場に入ります。実際にこんな上司がいたら大変ですが、近代化への熱い志を語りながら、現場で汗まみれになる姿が魅力的に描かれています。

井上勝鉄道局長を知らなくても十分に楽しめる作品です。私は、別の本で、偶然にも長州ファイブを知っていたため、より楽しく読むことができました。井上局長以外にも、カートライト機関士もお気に入りです。
幕末の長州藩から、ロンドン大学へ留学した五人のサムライ(井上馨、伊藤博文、井上勝、遠藤謹助、山尾庸三)の生涯と友情を綴った良書です。
檜垣澤家の炎上/永嶋恵美
横浜で知らぬ者なき富豪一族、檜垣澤家。当主の妾だった母を亡くし、高木かな子はこの家に引き取られます。商売の舵取りをする大奥様。互いに美を競い合う三姉妹。檜垣澤家は女系が治めていました。そしてある夜、婿養子が不審な死を遂げます。政略結婚、軍との交渉、昏い秘密。陰謀渦巻く館でその才を開花させたかな子が辿り着いた真実とは―。
- かな子・・・・檜垣澤要吉と妾の間に生まれた子。屋敷内の出来事に耳を澄ませる地獄耳。情報を武器に檜垣澤家で生き抜こうとする。
- スヱ・・・・要吉の妻で「山手の刀自」と呼ばれる女傑。檜垣澤家の家と事業を取り仕切っている。底の知れない人物。
- 花・・・・スヱの長女。スヱの跡継ぎとして事業を差配する。婿養子の夫には実権がない。
- 郁乃・・・・花の長女。花の跡継ぎだが、身体が弱い。
- 珠代・・・・花の次女。自由奔放で華族と駆け落ち騒動を起こした。
- 雪江・・・・花の三女。姉様ぶってかな子を可愛がる。
- 曉子・・・・華族の令嬢だが家が没落してしまった。かな子の親友。
明治時代・大正時代は現代と比較にならないほど、女性が生きづらい時代でした。そんな時代の中にあって、強く生きる女性たちが非常に魅力的です。檜垣澤を取り仕切るスヱや花はもちろんのこと、婚家にあって実家に富をもたらす女性たち、もちろん四面楚歌の檜垣澤家でのし上がろうとするヒロインかな子も力強く開花していきます。

私は、スヱとかな子が特に好きです。貧しい田舎出身で読み書きも出来なかったのに、「檜垣澤の家に男はいらない」とまで言わしめたスヱ。そんなスヱの背をみながら成長するかな子。二人の対峙するシーンは必見です
人魚は空に還る 帝都探偵絵図/三木笙子
「しずくは空に昇ってみたい」富豪の婦人に売られてゆくことが決まった見せ物小屋の人魚が、最後に口にした願いは観覧車に乗ることでした。しかし観覧車の頂上で人魚はしゃぼん玉の泡のように消えてしまいー(表題作「人魚は空に還る」)。風のように身軽で変装の名人、そして鮮やかな盗みっぷりで世間を風靡する怪盗ロータス。予告状に示された次の狙いは大邸宅の主人が集めた洋画でしたー(「怪盗ロータス」)。明治の世に生きる心優しき雑誌記者と超絶美形の天才絵師、ふたりの青年が贈る帝都物語。
- 里見高広・・・心優しき雑誌記者。天才絵師である有村礼の大ファン。
- 有村礼・・・帝都随一の美貌の絵師。気難しい性格。シャーロックホームズがお気に入り。
- 怪盗ロータス・・・変装の名人で、帝都で人気を博す怪盗。
里見高広は、とある縁で知り合った天才絵師、有村礼に、英国の雑誌「ストランドマガジン」に掲載されているホームズの話を聞かせてやったところ、礼はすっかりホームズを気に入ってしまいます。英文を読めない礼のために、高広はホームズを翻訳することになりますが、その見返りとして、礼は高広の雑誌社に挿絵を描いてくれることになります。
そして、ホームズが大好きな礼は、己をワトソン、高広をホームズと評し、遭遇する数々の事件の解決を高広に要求するのです。
一般的なホームズとワトソンのコンビ、いわゆる名探偵と助手の関係では、エキセントリックな名探偵と苦労性で真面目な助手という場合が多いものです。しかしながら本作では、『腰の低いホームズと高飛車なワトソン』と表現されているように、主役コンビの関係性が逆転しています。ホームズに事件解決をねだるワトソンといった二人の友情関係が、とても魅力的に描かれており、二人の掛け合いが楽しい作品です。

この物語は連作短編集で、高広と礼以外にも魅力的な登場人物が次々に登場します。中でも怪盗ロータスと彼と因縁のある青年の関係も必見です。
明治時代だからこその「見せ物小屋の人魚」や「神出鬼没の怪盗」という浪漫あふれる設定の物語で、表題の「人魚は空に還る」に代表されるように、人物や情景描写も明治時代のつかみどころのない不可思議さを儚く美しく表現しています。
また、コナンドイルがリアルタイムでシャーロックホームズを雑誌に掲載しており、礼がその翻訳を心待ちにしているという設定は秀逸です。

私たちの常識では、名探偵の代名詞となっているホームズですが、明治時代を舞台として、リアルタイムでシャーロックホームズの翻訳を楽しみにしているという設定にびっくりしました。確かにコナン・ドイルが雑誌に掲載している時代に生きていたら、礼のように続きが待ち遠しかっただろうと思います。よくぞこんな設定を思いついたものだと脱帽するばかりです。
シリーズ第2弾から第4弾です。タイトルだけでも飛びつきたくなる美しさです。また、回を追うごとに怪盗の出番が増えている気がします。
アイスクリン強し/畠中恵
舞台は明治23年の東京。築地の居留地で育った皆川真次郎は、西洋洋菓子屋・風琴屋を開きます。店には甘い菓子を目当てに幼馴染の旧幕臣である「若様組」がやってきては、騒動を持ち込みます。明治という捉えどころのない不可思議な時代のワクワク感と急転した世の中の理不尽さ、先が見通せないからこその若者たちの青春をポップで明るく描いた爽快感あふれる作品でした。本格派ミステリというより、謎がふんわり漂うような連作短編集です。
- 皆川真次郎・・・西洋洋菓子屋・風琴屋の店主。居留地で孤児として育ったため、英語や洋菓子作りが堪能。ミナと呼ばれるのが嫌い。
- 長瀬健吾・・・若様組の頭で真次郎の幼馴染。世が世なら大身旗本の若様であったが、維新後は出世の望めない巡査の身に甘んじている。
- 小泉沙羅・・・成金の娘。真次郎や長瀬の幼馴染。若様組のマドンナ的存在。

とにかく登場人物が全員魅力的でした。江戸の名残の漂う中で西洋菓子作りと語学が得意な真次郎。機転が利いて家柄も良いけれど、お金のない長瀬。成金の娘で袴姿で女学校に通う沙羅。他にも、若様組に無理難題を吹っ掛ける、沙羅の成金の父親。若様組の中でも抜群に容姿に優れているのに、乱暴者で危険な男、園山。などなど、主人公級の登場人物がひしめき合う物語です。
若様とロマン/畠中恵
「アイスクリン強し」の続編にあたる物語。平和に見える明治の世に漂いはじめた不穏な空気。成金の小泉琢磨は愛娘、沙羅の将来を案じて、戦争を回避しようと企みます。その秘策は、なんと若様たちのお見合い!一筋縄ではいかない成金の琢磨に振り回されながらも、懸命に時代を生きる若者たちの姿が、可笑しくもどこか羨ましく感じられる作品でした。

前作に続き連作短編で読みやすく、あと数ページでどう決着をつけるのか先が読めずに楽しく読了できました。今作では、真次郎や沙羅、長瀬といった若者たちが、将来に向けて一生懸命奮闘します。おばちゃん目線では羨ましくなるほどキラキラしていて、読んでいるだけで元気をもらえる物語でした。
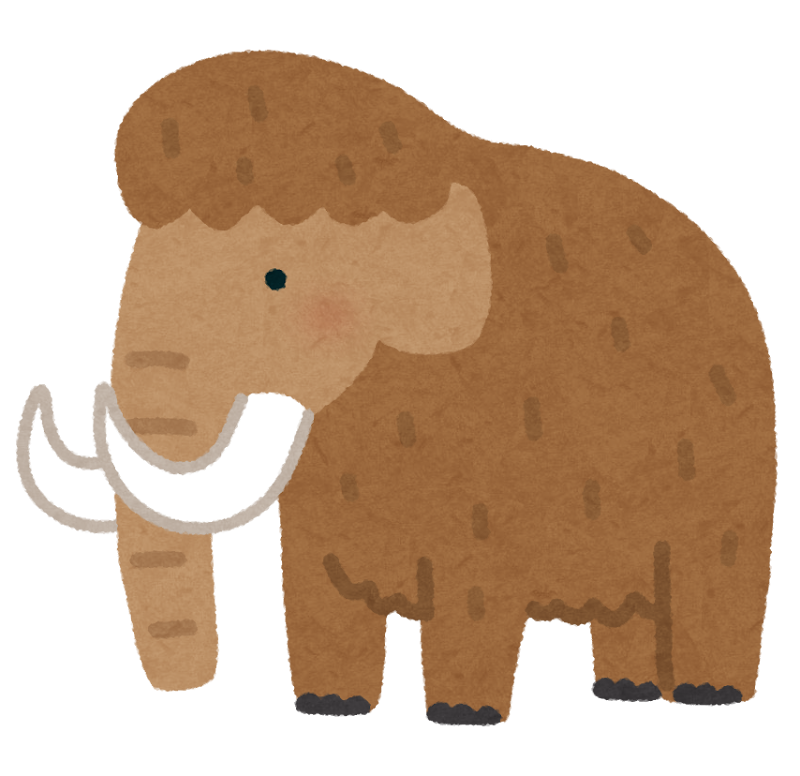



コメント